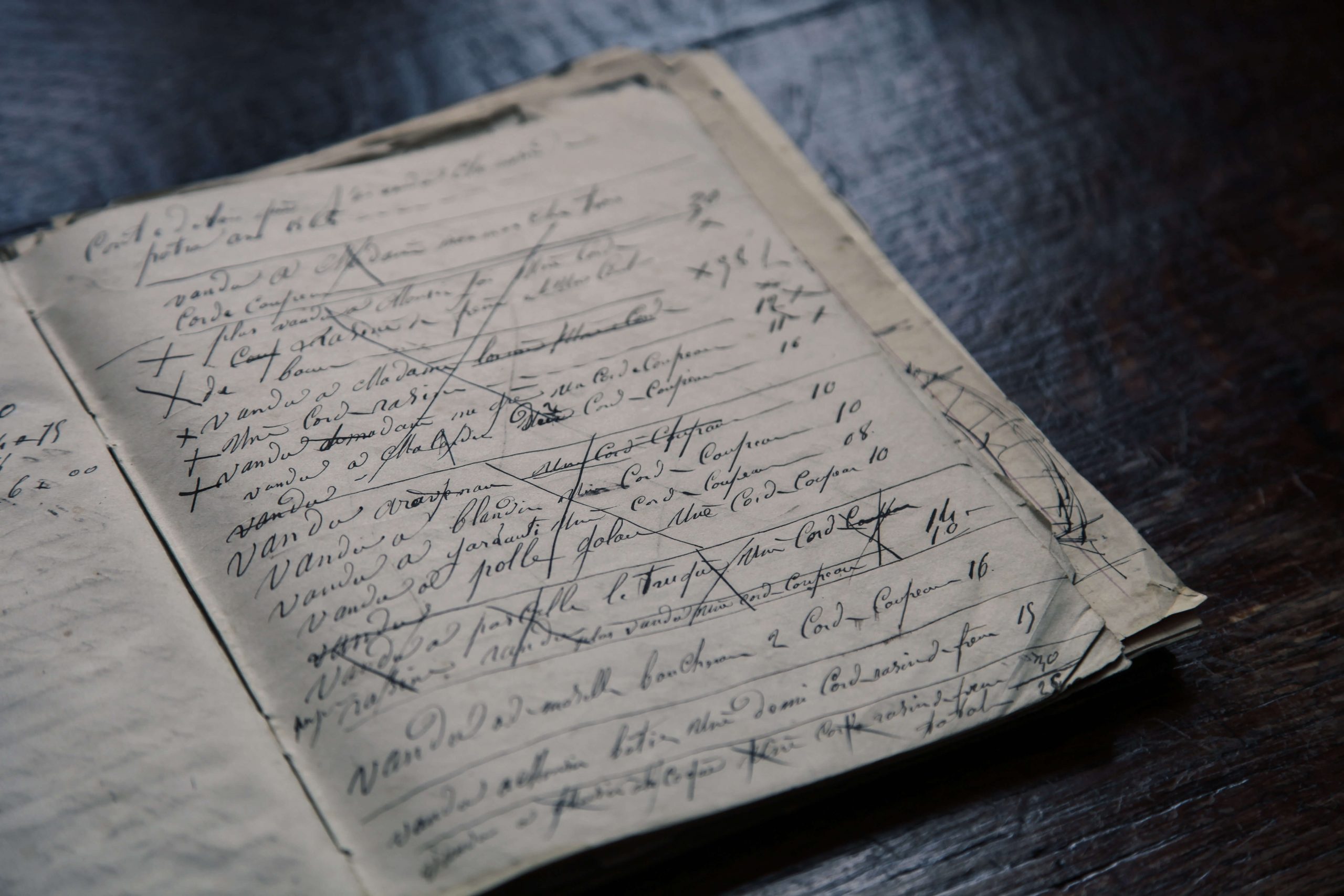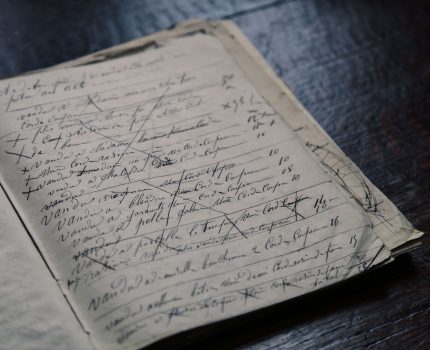3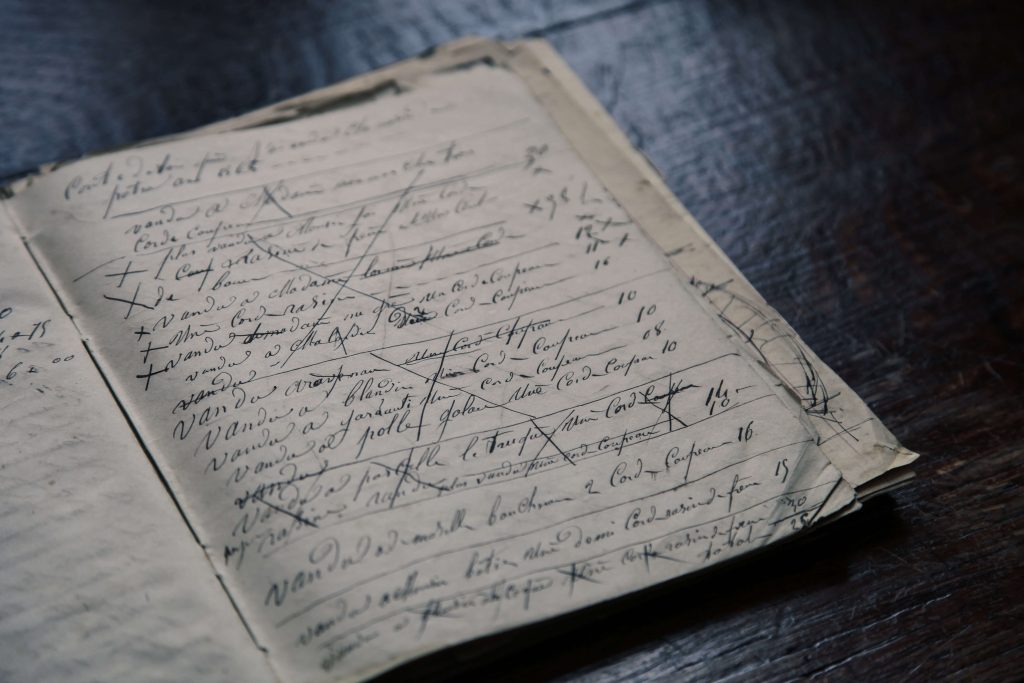
英語が上達する人としない人の差は、ここにある
先日、Twitter上に
「何冊も参考書買わない方がいいですよ。
それよりも1冊を何十回と繰り返して中身を全部頭に入れる。
入れたら、練習問題で出しまくる(アウトプット)訓練をした方が、英語のテスト問題は解けるようになります」
(一部抜粋)
という投稿がありました。
私もそう思います。
でも、過去は違いました。
「参考書や問題集はあればあるほどいい」
と思っていたタイプです 笑
たとえばTOEIC満点を目指していた頃。
TOEICと名の付く問題集はくまなくチェックし、模試に至っては国内モノはすべて購入。
それだけでは飽き足らず、韓国模試も、ネットで検索して相当買いました。
現地から取り寄せたものも多々あります。
「1冊を徹底してやるより、1問でも多く解きたい」
量をこなすことに必死で、がむしゃらで、そこにしか目が向いていませんでした。
でも、スコアが上がらず、むしろ下がったり。
そのジレンマに長いこと苦しめられてきました。
一見、問題を大量に解くというのは正攻法にも思えます。
たくさんの問題に触れる=知識が増えていく、実力がつく
と結びつけがちですよね。
が、デメリットもあります。
まだ弱点をつぶし切れていないのに「量」にこだわるあまり
・すでに解ける問題ばかりやったり
・間違えたものがあっても、解く数にこだわるあまり、丁寧に復習しない
こういうことが起こりえますし、私はまさにこの状況でした。
まるで
「ざるを使って必死に水をすくおうとしている」(=実が取れない)
ような感じです。
当時のことを振り返ると、こんな印象があります。
「大量に解く」ことに盲目になってしまっていたんですね。
今は、冒頭のツイートのようなことをしています。
「1冊を何十回と繰り返して、丁寧に勉強する」
英会話であっても、文法であっても、テスト用の問題集であっても、そうやって勉強しています。
厳選したテキストや問題集だけを手元に置いて。
それを繰り返し繰り返しやっています。
ただ、単純作業をやるわけではないですから、同じように繰り返すのではなく、常に視点を変えます。
そのテキストに向き合うたび
・自分は何がわかっていないのか
・今わかっていること、できていることは何か
・この課題(問題)をクリアにするにはどうアプローチしたらいいのか
最低この3つは常に頭においた上で、練習します。
同じものを使っても、実力がつく人とつかない人の差はどこにあるのでしょうか。
それは「使い方の違い」にほかなりません。
料理に例えるなら、プロの料理人は仮に冷凍食品やインスタントものしかなかったとしても、ちょっとした工夫とテクニックで、レストランのそれと遜色ないほど、素晴らしい料理を作ることができます。
手元にある素材をどう使うか。
「今の自分のサイズ感だったら、どういう風に使うと効果が出るか」
ということです。
これを真剣に考えて実践することで、英語力はついてきます。
それを体感すると
「ああ問題集ってそんなにいらないんだな」
と、心から感じることができます。
これはやってみた人だけがわかる感覚だと思います。
それをやってから、大量に問題を解き、色んなバリエーションのものに当たれば、鬼に金棒です。
ツイートした方は、おそらくそういう意図で書かれたのだと思います。
まずしっかり足元を見て。
自分の立ち位置を確認するところから始めましょう。
すべては、ここから。
少しでもご参考になれば幸いです。
ここまでお読みくださりありがとうございます😊
//////////////////////////////////////////////////////
■Akiの英語メルマガ
英語学習に必要な心・技・体についてのtipsをお届けする無料メルマガを発行しています。
お申し込みはこちら↓
■オンラインサロンAki塾
現在、メンバー募集中です。
当サロンは、継続するマインドを身につけ、自信を持てる自分になることを目指していく場所。
自分の内側と向き合い、人生を好転させていくための「胆力」を養う。
サロンに入会されると、次のようなことを体感できます。
・継続できる自分になれる
・自分だけの目的や目標(英語に限らず)を持つことができる
・モチベーションを維持できる仲間とのつながりが持てる
・心を整え、人生を好転させていくための知識が得られる
・中学からの基礎文法知識を得られる
・音読のコツが学べる
・転職や起業、海外移住に関する最新情報が得られる
皆さまのご参加、お待ちしております。
■コーチング
1対1のコーチングも承っております。
・英語学習のモチベーションを維持するのに苦労している
・英語が話せるようになるために、何をどのように勉強したらいいかわからない
・英語学習の目的を見失っている
・英語学習の習慣を継続できない
・TOEICや英検などの英語のテストにチャレンジしたい(している)ので、効率のいい勉強方法を知りたい
こういったお悩みをお持ちの方、私が伴走させていただきます。
ズームによる無料カウンセリングでコースの詳細をお伝えしていますので、ご興味がある方は
stoiceraki@gengomanabi.com
こちらのアドレスに
件名に「無料カウンセリング希望」、及び本文にお名前(ニックネーム可)を記載してお送りください。
速やかに返信させていただきます。
※毎月の人数は数名となっておりますので、順番待ちをしていただく場合がございます。
■書籍
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////